栃木県下有数の進学校から現役で東京大学理科I類に進学し、エネルギー関係の企業に研究職として入社後、社費で米国大学院へ留学した経歴をもつキャリア社員が、突如として辞職を願い出たのである。

しかも、その理由が、
「子育てのために自分が会社を辞めることにした」
だったから、社内に大きな波紋が広がった。実は、本当の理由が別にあってそれを隠しているのではないかと詮索されたという。
「理解はできるけど、どうも納得できないね…」というのが、井口さんが辞意を伝えたときの社内での反応だった。
栃木県下有数の進学校から現役で東京大学理科I類に進学し、エネルギー関係の企業に研究職として入社後、社費で米国大学院へ留学した経歴をもつキャリア社員が、突如として辞職を願い出たのである。
しかも、その理由が、
「子育てのために自分が会社を辞めることにした」
だったから、社内に大きな波紋が広がった。実は、本当の理由が別にあってそれを隠しているのではないかと詮索されたという。
|
幼い頃は好奇心が強い子供だった。なんにでも首をつっこむのだが、 「自分が好きになったもの以外は、見向きもしなかったんですね」 ゴミ捨て場から廃品のモーターを拾ってきて、中に入っている磁石で遊んだり、木工に夢中になった時期もあった。新聞受けに始まり、椅子まで作ってしまったというから大した小学生である。小学校高学年になると、父親の影響で電子工作に夢中になり、真空管ラジオを作ったりした。 学校の勉強のようにきちんとやらなければならないものは苦手だったという。ただし、勉強しない割には成績の方は悪くなかった。先生からは「まじめにやれば、もっといい成績がとれるはずなのに」といつも言われている子供だった。勉強には「関心が向いてないから」やる気にならなかったという。 たとえば、理科とか算数とか主要科目でも好きなところは、「とことん掘り下げて」勉強するのだが、試験範囲をすべて網羅するように「穴を埋めて」いくような勉強のやり方ができなかったという。 |
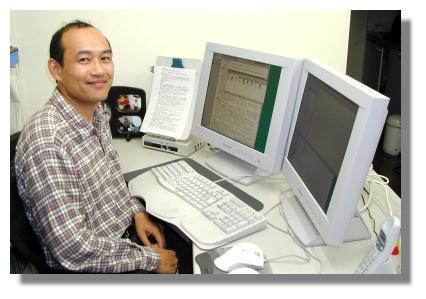

【 後編につづく 】
(取材・文 加藤隆太郎)
|
【前編】 【 後編 】 |
|
※この記事のオリジナルは、日外アソシエーツ発行の読んで得する翻訳情報メールマガジン「トランレーダードットネット」に掲載されたものです。お問い合わせはこちらまで。
[ 戻る ]
Counter
since 12/21/2000