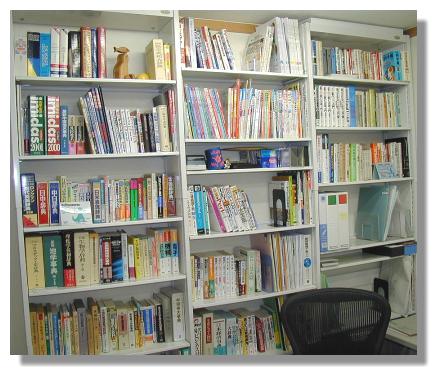米国の大学院に入学するには、文系でTOEFL600点以上、理系ではTOEFL550点以上が入学の要件になる。

夏頃、同期入社の数人で力試しにTOEICを受験していたのだが、スコアは650くらいだったという。TOEFLに換算するとやっと500点を超えるくらいだろうか。
大学受験で使っていた参考書を見直してみたら、「基本的な文法もわすれていたんですね」
当時、井口さんは研究所に併設の寮に住んでいたのだが、研究所は木更津市(千葉県)から車で30分くらいの僻地にあったし仕事が忙しかったので、夜間に英語の学校に通うということもできなかった。
秋から一生懸命勉強を始めて、通勤時間を利用してFENを聞いたり、帰宅後に参考書をめくったりして努力を続けた。
「2月に受けたら553点。ギリギリだったんですね(笑)」
かろうじて入学要件をクリアしたわけだ。春に別件で米国出張した際に、現地の情報を収集し、帰国後、会社と相談した結果、オハイオ州立大学が留学先となった。井口さんが大学で研究していた装置の研究者がいたのだ。