『翻訳の世界』元編集長 今野哲男さんにきく
翻訳雑誌と翻訳教育産業
【今野さんのプロフィール】……1986年株式会社バベル入社。『翻訳の世界』(eトランスの前身)編集部に在籍し、1993年から編集長を務める。現在はフリーの編集者として、地道に取材・執筆活動を続ける傍ら、インターネットを使った通信教育システムの開発にも携わっている。
◆ 月刊誌『翻訳の世界』創刊
『翻訳の世界』が創刊されたのは、株式会社バベルの前身「日本翻訳家養成センター」の創業とほぼ同時期の70年代中頃のことです。僕は創刊当時から社員だったわけではないのですが、当初はA5版で活版印刷の雑誌でした。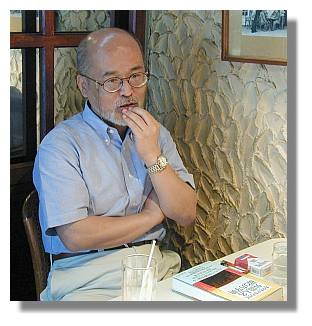
最初の1、2号は創業者の社長が編集長をかねていましたが、すぐに杉浦(洋一)さんという方が二代目の編集長に就任されました。その後7、8年は杉野さんの時代が続きました。それが『翻訳の世界』の第1期ということになるでしょう。
雑誌の中身は、70年代は文化人類学が非常に元気な時期ですから、その影響からか比較言語学的な視点が強かったと思います。通信教育のPR誌という側面は確かにありましたが、単なる広報誌レベルの雑誌ではなかった。はじめから本格的な翻訳雑誌を目指していて、学術誌に近いような面があったと思います。
ページをめくっていくと本扉といって、雑誌の中に扉がついていました。これは、『文学界』とか『文芸』とか『群像』といった文芸誌の体裁と同じなんですね。だから体裁の面から見ても、文芸的な志というのが当初からあったと思います。翻訳を学習技術的な面だけでとらえるのではなくて、比較文化学の観点から論じて伝えましょうという姿勢ですね。バックナンバーを見ても、当時の特集にはその手のものがけっこう多いと思いますよ。執筆陣をみても、翻訳家だけではなく小説家や詩人、学者といったそうそうたる方たちが記事を書いていました。それが骨格となって、その上に、翻訳技術論とか通信教育論が展開されていたわけですね。
(青木)
そうすると、翻訳に興味がある人や、翻訳家になりたい人が読む雑誌ではなかったのでしょうか。
学習者向けなのですが、直接の教材という位置づけではありませんでした。通信教育の受講者にも定期購読の勧誘をしていたわけですが、受講生の全員が購読しているというものでもなくて…。学習者にすると、どうも堅苦しくて難しいからついていけないという時代があったんです。それで良しとしていた時代があったんですね。
(加藤)
たしかに、当時の学習者には敷居が高かったようですね。でも、逆に、一般読者にとっつきにくい誌面だからこそ、翻訳の世界というブランドが確立されて、その強力なブランド力に惹かれて受講者が集まっていたという構図があったようですが…。
そうかもしれません。ただ、あの志は、当時の時代背景に即した貴重なものだったと思いますね。
◆ ジャーナリズムの視点
85年に、編集人が三代目の丸山(哲郎)さんに代わって、活版印刷中心からビジュアルも意識した写植中心のB5判型の雑誌になりました。
それで、比較文化論的な色合いをやや薄めて、もっとジャーナリスティックにやろうよというように、スタンスが徐々に変わっていくんです。当時は身近なところで国際化が盛んに叫ばれるようにようになって、掛け声だけではなくて、実際に日本の企業がどんどん海外に進出していくようになっていました。メディアにしても、ニューズウィークの日本版が登場したり、ケーブルTVが普及したり…。ジャーナリスティックに翻訳を取り上げるための取材対象に事欠かなくなってきていたわけですね。機械翻訳の登場などもありましたから。
(加藤)
当時は、機械翻訳関連の記事が誌面を大きく飾っていましたね。(第1次機械翻訳ブーム)
たしかに当時の『翻訳の世界』では、産業翻訳関係では機械翻訳が一番大きなトピックだったかもしれません。丸山編集長の時代に、大きな特集を3回ほどやっていますから。
機械翻訳は90年頃に注目されて、その後2、3年のうちに社会の評価がどんどん変わっていきました。最初のうちは、機械翻訳で人間と同じことができるんじゃないかという期待感があったんですね。翻訳のできるAI(人工知能)が登場するんじゃないかって…。それで翻訳関係者の間では、AIというのはすごいという期待感で騒ぐ人たちと、いや、この機会にそもそも翻訳とは何なのかということをもう一度原理的に反省してみたいという人たちの、二つの流れができたわけです。
『翻訳の世界』の特集はその二つの流れの狭間で行ったものですね。もっとも、当の開発者には、そんな認識はあまりなくて、AIが実用化するとしても100年先の話だよなんて言っている人もたくさんいましたが(笑)。しかし、当時は機械翻訳で人間と同じことができるんじゃないかと、真剣に考えていた人がいたことは確かでしょうね。
 で、そうこうするうちに、翻訳ソフトや辞書ソフトがパソコンに組み込まれて廉価になり、パソコンなしでは翻訳ができない時代に移っていくわけです。機械翻訳の翻訳能力上の限界は承知の上で、検索や保存・修正といった使いやすさの点でマシンの特性を精一杯利用しましょうということになったわけですね。皮肉なことだけれど、機械翻訳がもつ能力への期待が裏切られたところで、かえってパソコンの本当の普及が始まったわけです。それで、キーボードがまるで翻訳者の手の一部のようになっていく。マシンが翻訳者の中で身体的に内部化していくわけですね。
で、そうこうするうちに、翻訳ソフトや辞書ソフトがパソコンに組み込まれて廉価になり、パソコンなしでは翻訳ができない時代に移っていくわけです。機械翻訳の翻訳能力上の限界は承知の上で、検索や保存・修正といった使いやすさの点でマシンの特性を精一杯利用しましょうということになったわけですね。皮肉なことだけれど、機械翻訳がもつ能力への期待が裏切られたところで、かえってパソコンの本当の普及が始まったわけです。それで、キーボードがまるで翻訳者の手の一部のようになっていく。マシンが翻訳者の中で身体的に内部化していくわけですね。
(青木)
編集の仕事もずいぶん変わったんでしょうね。
昔は、手書き原稿だったのですが、悪筆家が多くて…(笑)。担当の編集者にしか原稿が読めないということもありました。どうしても読めない字があると電話で問い合わせたり、それが担当編集者の仕事の一部だった。ともかく毎月印刷所まで出向いて、出張校正をしていたんですからね。お祭りのようで、僕は好きでしたけども(笑)。
(青木)
今は編集部でもパソコンを使って作業をするのが当たり前ですからね。
50代から下くらいの世代は、パソコンにあまり抵抗感がないんでしょうね。そういえば、『翻訳とは何か』の山岡洋一さんも、当時は機械翻訳の辞書を作っていた人なんですよ。
(青木・加藤) へぇー………(絶句)。
◆ 翻訳家が女性のあこがれの職業だった時代
(青木)
今野さんはいつ頃から『翻訳の世界』の編集に携わるようになったんでしょうか?
70年代は読者の側にいたんです。翻訳家を目指していた時期が少しありまして…。その後、株式会社バベルに入社して雑誌の編集に携わるようになりました。
(加藤)
当時のバベルは、翻訳教育産業における巨人だったという印象がありますが。
フェローやユニ・カレッジなど、他の学校もありましたが、文芸翻訳の方面では自他共に認める最大手でした。毎月、朝日新聞の日曜版に大きく広告を出稿していましたし…。当時はバベルが一番目立っていましたね。
(加藤)
無料翻訳力診断の綴じ込みハガキは一世を風靡しましたね。あれが、当時の翻訳教育産業を象徴していたと思うんです。
80年代から90年代前半までは、あのやり方で人が集まっていたんです。それが、だんだん集まらなくなっていく…。90年代の前半までは、翻訳学校には、有名な翻訳家や大学の先生による個別指導や進路の世話が受けられるという要素があって、学習者が望めば、そのような一流の先生の講義を寺子屋的にうけられました。それが、徐々に講座の修了生で成績の良かった人に、講師をやらせるように構造転換していったんです。一種のリサイクルですね。
(加藤)
先生がその学校の出身者なら、受講生の側から見て、自分もがんばればプロになれるんじゃないかと希望がもてるという効果もありますね。
だから、翻訳が女性のあこがれの仕事という時代があったんですよ。トレンディドラマでもヒロインの職業が翻訳家ということがあり、戸田奈津子さんや山本やよいさんがあこがれの的だった。
なんていうか、国際化という言葉が死語化してしまったことからもわかりますが、90年代になって国際的なコミュニケーションが身の回りに日常化した結果、かつてのような翻訳家という職業にエキゾチックなあこがれをもつというメンタリティが社会から無くなってしまったんだと思うんです。それで、文芸翻訳のようなお金とは無縁のものよりも、産業翻訳という確実に稼げる方に関心が集まるようになっていった。
そのような背景があるために、雑誌には、仕事を得るためのハウツーとか情報提供とか、翻訳者になるためのマニュアル的な要素が占める割合が多くなっていきましたし、かつてのように綴じ込みの無料診断ハガキから受講に誘導していこうというやり方にも勢いが無くなったんだと思います。翻訳志望者のパイが減ったのも、結局そのせいじゃないかな。
(加藤)
世相もあるんでしょうね。不況が長引いて雇用不安が深刻になると、みんな夢や憧れよりも現実的な方向へ目を向けるようになる。それで産業翻訳にスポットが当たるわけですか。
産業系では、イカロス出版の月刊誌『通訳翻訳ジャーナル』、あとはアルクさんから時々ムックが出てますね。
(青木)
イカロスさんはもともと航空関係の出版社で、スチュワーデス志望者向けの雑誌をつくっていて、スチュワーデスなら英語、そこから、通訳・翻訳の雑誌を出そうという発想が出てきたようですね。
ええ、スチュワーデス志望者だった人に陸に上がってもらって、英語の仕事なら通訳か翻訳だってあるじゃないかいうことでしょうね。イカロス出版には『外語スペシャリスト』という本もありましたから。
(青木)
翻訳の世界も、文芸なら、文芸だけで押し通すという手もあったんじゃないでしょうか。
いや、以前のまま続けるのは、無理だったでしょうね。
バベルは翻訳会社も持っています。翻訳会社の主たる売り上げが何かと言ったら、やはり産業翻訳なんです。文芸翻訳もありますが、売り上げ額のポテンシャビリティを考えれば、日本の企業活動全般に関わっている産業翻訳に比べて、それほどの規模があるわけではない。ビジネス効率の点から考えても、産業翻訳と文芸翻訳とでは比較になりません。そんなことと、80年代に翻訳がもっていた魅力の変化という事情をあわせて考えてみると、やはり産業翻訳を無視することはできなかったと思いますね。
◆ 出版業界の現状
翻訳に限らず出版物の点数は増えていますが、一点あたりの部数は減っているんじゃないですか。誰の話を聞いても、増刷がないよって言いますし…。
(青木)年間4万点だったのが、少し前に5万点になって、今では6万点ぐらい出ているそうですね。
回転はしているけど、初版で終わってしまう…。
(青木)手形みたいなもので、新刊と返品とで相殺するわけですよ。
自転車操業をしないと回っていかない。出版社が取次経由でやっていくためには、そうなってしまうんですよね。インフラがそうなってるから…。文庫の翻訳エンターテイメントだと、書店の棚の問題があって毎月出していかないとどうしようもないという現実もあります。
(青木)一方で、今は、新古書店がどんどん進出しているので、そういうところで買えばいいということになってしまいますね。
話題の新刊でも1ヶ月か2ヶ月待っていれば、新古書店の店頭に並んでいるということがありますよねぇ。CDもそうだし…。
僕は、著作権の考え方がいずれ変わってくるような気がしますね。今までは、著作権への対価を、著者にだけ払ってきたと思っている人が多いかもしれないけど、実は丁寧に製本して、流通経費をかけて書店の店頭に並べて、お客様に商品として差し上げるためのインフラにかかる経費というのがすごく大きくて、実質はそれに払っている部分が相当あると思うんですね。
今は、そんなインフラはなくたっていいわけで、ネット上のWebサイトで流通させたりという方法があるわけです。ところが、ネットの情報に金を払うかというと、基本的には払いたくない人が多いわけですよ。そうなると、従来の書籍の値段というのは実はインフラに払っていた部分が多くて、全てを著者に払っていたわけではないという考え方が可能だと思うんです。そうなると著作権とはいったい何なんだろうという疑問がでてくる。
インターネットを見ていても、著作権云々をうるさく謳ってホームページをつくっている人というのは何か「うざったい」感じがあるでしょう?
どうも遅れているという感じがするんですよね。そういう感覚はみんなが持っていると思うので、時代がもしかしたらそっちの方向に動くんじゃないかという気がしますね。
僕はテキストで今まで通りの金を寄こせというのは無理があると思うんです。その意味では、著者は昔ほど偉い存在ではなくなっているんじゃないでしょうか。これは半分冗談ですが、世間で大騒ぎしている知的所有権の問題って、実は、著作権というものの金銭的価値が疑われていることの裏返しじゃないですか(笑)。そのあたりをよく考えておかないと、翻訳をしている人や作家は、道を間違えてしまうことになるかもしれませんね。
僕は今、「人間総合科学大学」という通信制の四年制大学の仕事をしていて、アメリカの通信教育について調べる機会があるんです。米国は社会のインターネット化がかなり進んでいるので、たとえば、論文を書く課題を与えられると、みんなインターネットを使って調べものをするわけです。で、中にはネット上にある情報を寄せ集めてきて、コラージュで論文の骨格を作る人がいて、そのためのマニュアルを作って販売している会社まであるんですね。それでその同じ会社が、コラージュで作った論文を見分けるためのマニュアルも用意していて、教官たちが結構買うらしい(笑)。まあ、商道徳も糞もないわけですが、通常の商業倫理的な問題を超越しているところが、過渡的でかえって面白いと思いますね。
(青木)メルマガで取材活動を続けている目的のひとつとして、翻訳という職業で、経済的な意味で、あるいは名声という意味で成功した方をモデルとしてとりあげようという意図があったのですが、実際、取材を重ねていくと、現実は厳しいという印象を受けますが…。
本を1冊、きっちり訳すとなると、基本的に3ヶ月に1冊くらいのペースになるでしょう。それ以上はちょっと無理でしょうね。だから年間4冊として、文庫本で3、4万部がやっとというのが実状でしょう。それで翻訳者の印税はよくても8%、今は4%とかいうところもあるようだから…。
(青木)それで、3ヶ月かけて働く価値があるかと言われると、経済的には、考えてしまいますね…。
翻訳家に限らず小説家も同じじゃないですか。表現系の文筆生活者にとっては押しなべて受難の時代なんですよ。今までが良すぎたという考え方もあるでしょうけれど(笑)。
(青木)出版社でも、他に確実な収入源を持っていらっしゃる人の方が、本を書くという、さほど収入にならない仕事をお願いしやすいということもありますから…。
かといって、自分が書いたものをネットで有料配信するのも、なかなか難しいと思うんですよね。山岡(洋一)さんが『翻訳通信』を有料配信されるそうですが、どうなるか楽しみですね。
(加藤)山岡さんの翻訳通信は、翻訳者の間でも話題になっていますから、有料でも読みたいという人がけっこういるんじゃないでしょうか。
でも、山岡さんがそれにかける時間を時給計算したとしたら、当面はとても合わないということになるんじゃないですか。だから、山岡さんの目的は、もっと別のところにあると思うけれど…。
(青木)月に2回くらいが限度でしょうから、有料だと休むわけにもいきませんし…。
作家でも、村上龍がネットで活動していますよね。あれは、直接それでお金をもうけようとしているわけではなくて、あそこで人材や読者を集めておいて、別の場所でイベントをやったり、本を作ったり、社会的な提言をすることで、成り立っている部分があると思うんです。村上龍に限らず、ネット上のテキストを直接お金に換えようという考え方から自由な方が、活動が魅力的なのではないですか。
じゃあ、翻訳もそれがやっていけるのかということになるんでしょうが、翻訳には原著のテキストという重石がありますからねぇ(笑)。そういう融通性はないかもしれないですよね。ネットで翻訳して別の場所で翻訳論を語るとか、あるいはその逆とかいうことになるんでしょうか。
◆ コミュニケーション手法としてのインタビュー
(青木)差し支えなければ、翻訳の世界の編集から手を引いたきっかけをお話しいただけませんか。
退社前から業務上は雑誌とは無縁の立場になっていましたから、自ら手を引いたわけではないんです。僕自身は、本音のところではたとえ時代に逆行しても、以前の『翻訳の世界』を引きずったところがあった方がいいと思っていましたから。だから、退社したのは、時代が僕をリストラしようとしたので、自尊心から先手を打ったということじゃないかな(笑)。
『翻訳の世界』でやっていたことを一言でいうと、「翻訳はコミュニケーション」だということです。横のものを縦に置き換えるという言語技術的な話だけではなく、人と人とのやりとりに興味があったんです。具体的に言えば、インタビューをやりたかった。
ここで言うインタビューとは、雑誌の取材者として行う狭い意味でのインタビューに加えて、教育や行政や医療現場や教育現場で行われている様々なやり取りも含んでいます。子どもの問題とか、医療過誤の問題が、実は、ひとつひとつの話し言葉のやりとりの場で、コミュニケーションが阻害されておきているんじゃないかと思っていたので、インタビューを実践しながら、同時にこの問題を原理的に考えてみたいと思っていたんですよ。
産業翻訳の方面へ行くと、インタビューという形式自体はあっても、その機能がどうしても情報伝達に偏りがちでしょう。でも、自分では、情報伝達の面だけではなく、人間存在や表現の面からも考えてみたかったということですね。
通信教育というと、マスプロ教育の権化のように思われることも多いのですが、そうではなくて実は通信教育ほど一対一のコミュニケーションが必要な教育はないと思うんです。スクーリングのような機会で、1対100くらいで対面授業をやるよりも、メールを使って1対1で、濃密なコミュケーションをやった方が、コミュニケーションという観点から面白いということがけっこうありますから。
(青木)一方的な情報の発進ではなくて、双方向のコミュニケーションということですね。
そうですね。今は、「人間総合科学大学」で、卒業研究指導のためのシステム開発や教科書制作のディレクションをしながら、同時にいくつかの雑誌でインタビュー記事を担当しているのですが、この大学が目指している「こころ」と「からだ」と「文化」の統合という教育理念に、自分の思うインタビューという考え方がどう触れあっていくのか、時代の流れの中で、いずれ形にしてみたいと思っているんです。
(聞き手・青木竜馬 取材・構成・文 加藤隆太郎)
※ 【コラージュ】大辞林第二版より
新聞・布片・針金など絵の具以外のものを様々に組み合わせて画面に貼りつけ、特殊な効果を出す現代絵画の一技法。
※この記事のオリジナルは、日外アソシエーツ発行の読んで得する翻訳情報メールマガジン『トランレーダードットネット』に掲載されたものです。お問い合わせはこちらまで。
[ 戻る ]
e時代  since 12/21/2000
since 12/21/2000
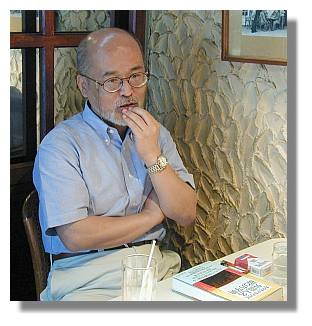

 で、そうこうするうちに、翻訳ソフトや辞書ソフトがパソコンに組み込まれて廉価になり、パソコンなしでは翻訳ができない時代に移っていくわけです。機械翻訳の翻訳能力上の限界は承知の上で、検索や保存・修正といった使いやすさの点でマシンの特性を精一杯利用しましょうということになったわけですね。皮肉なことだけれど、機械翻訳がもつ能力への期待が裏切られたところで、かえってパソコンの本当の普及が始まったわけです。それで、キーボードがまるで翻訳者の手の一部のようになっていく。マシンが翻訳者の中で身体的に内部化していくわけですね。
で、そうこうするうちに、翻訳ソフトや辞書ソフトがパソコンに組み込まれて廉価になり、パソコンなしでは翻訳ができない時代に移っていくわけです。機械翻訳の翻訳能力上の限界は承知の上で、検索や保存・修正といった使いやすさの点でマシンの特性を精一杯利用しましょうということになったわけですね。皮肉なことだけれど、機械翻訳がもつ能力への期待が裏切られたところで、かえってパソコンの本当の普及が始まったわけです。それで、キーボードがまるで翻訳者の手の一部のようになっていく。マシンが翻訳者の中で身体的に内部化していくわけですね。


since 12/21/2000